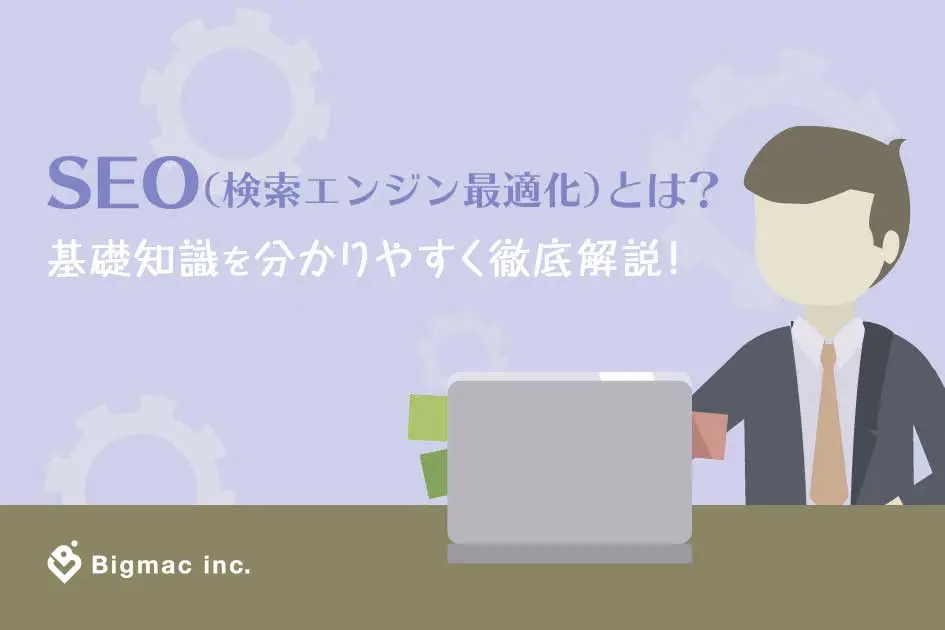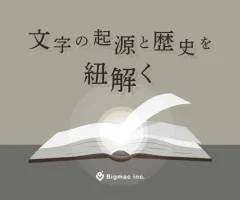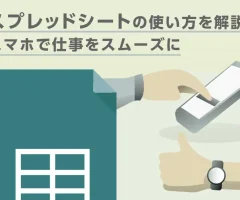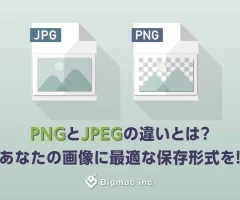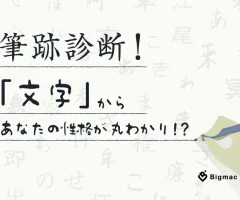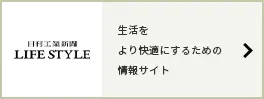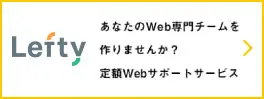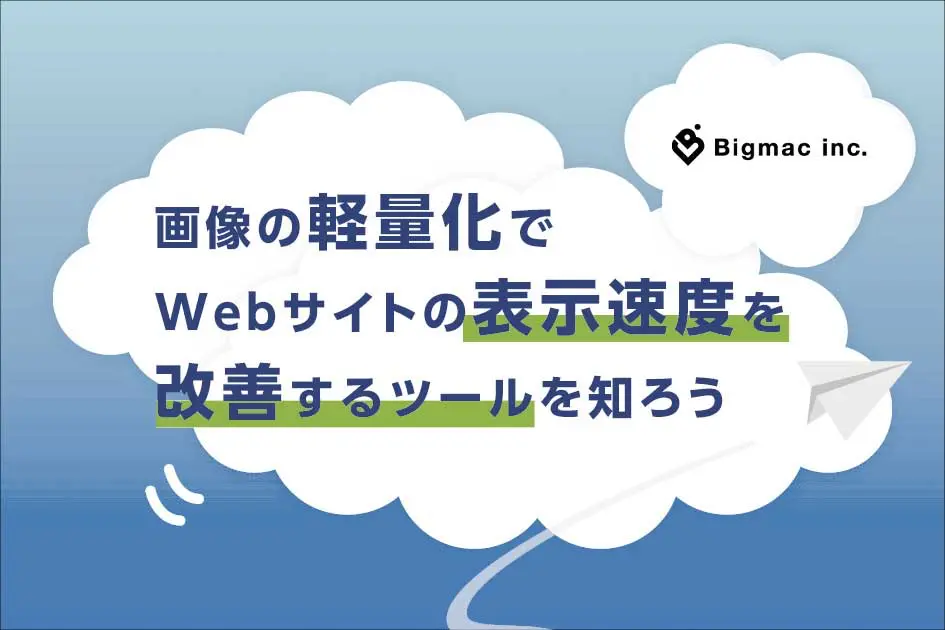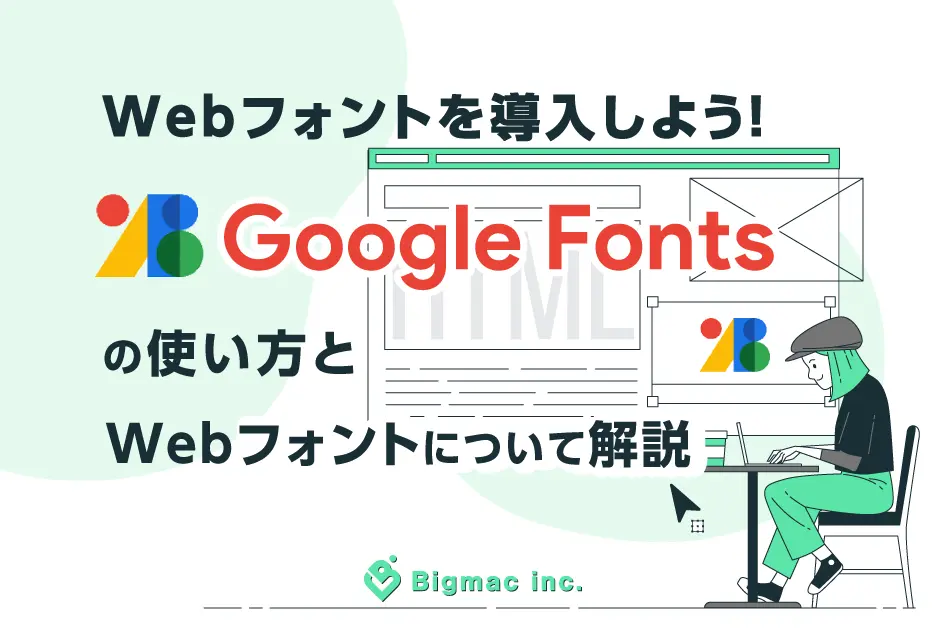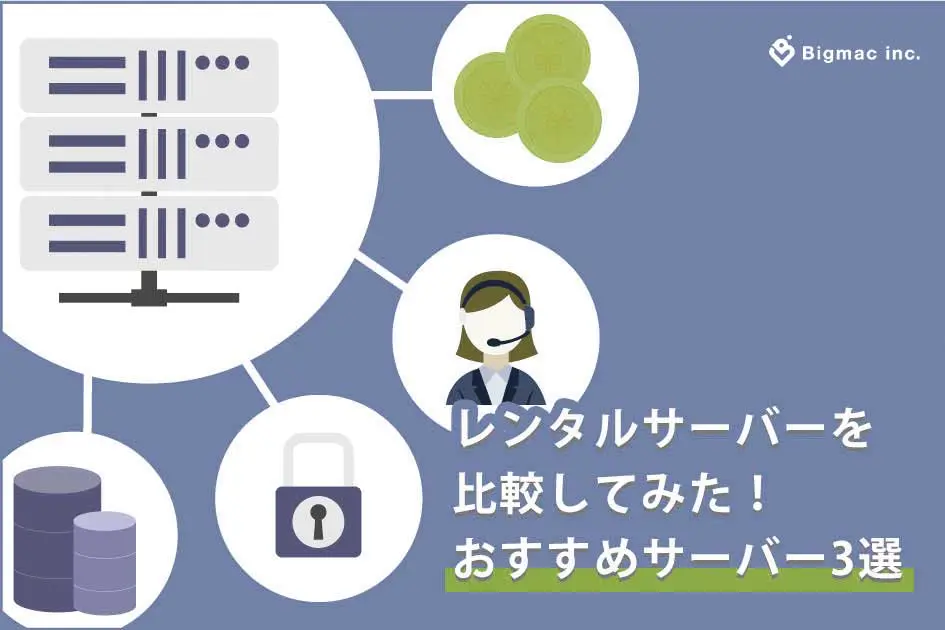サイトやブログを運営する上で、著作権や肖像権が気になることはありませんか。
ネット上に公開されている写真を勝手に使用して、後から問題になっては困りますよね。
想定外の利用料が請求されたり、記事の削除を求められたり、最悪の場合は裁判になることもあり得ます。
著作権や肖像権は、サイトやブログ、ひいては会社や運営者の信用を下げることにもなりかねない問題です。
目次
著作権と肖像権の違い
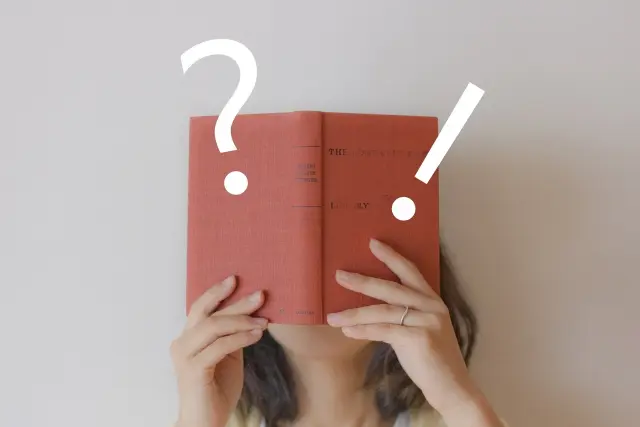
文章をよそのサイトから完全にコピー&ペーストすれば著作権法違反になることはわかると思います。
しかし、部分的に使用する場合はどうなるのでしょうか。
また、写真の場合は、著作権はあるのでしょうか。
著作権とは別に肖像権という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。
簡単に言えば、著作権は文章や写真など、何かを作った人を守るものです。
一方、肖像権は写真などの被写体になった人を守る法律です。
著作権も肖像権も、サイトやブログを運営するうえで必ずクリアしなければならない法律です。
最新情報をいち早くお届け!
無料会員登録していただくと、
会員限定の特別コンテンツ記事を最後まで
読むことができます!
その他、更新情報・イベント情報を
お届けいたします。
著作権とは
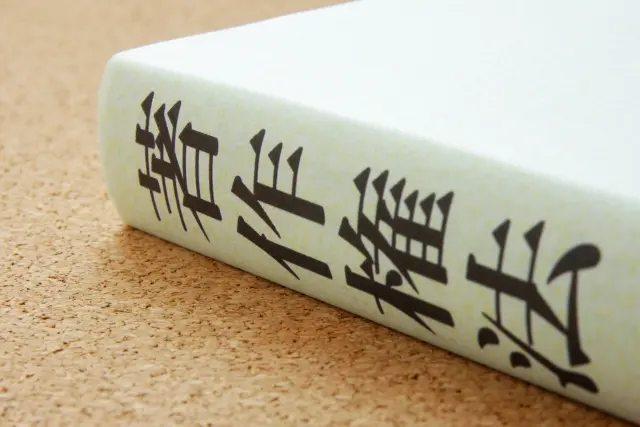
著作権とは、文化的な創作物を保護対象とする権利で、著作権法で保護されています。
文化的な創作物というのは、文芸、学術、美術、音楽を指します。
著作権の保護対象は多岐にわたります。
下記はその一例です。
・詩
・論文
・脚本
・写真
・絵画
・彫刻
・図面
・デザイン
・模型
・映画
・音楽
・ダンス
・パソコンのプログラム
音楽や演劇であれば、CDやDVDなどの録音・録画されたものだけでなく、実演そのものも著作権法の適用範囲に含まれます。
なお、憲法その他の法令、裁判所の判決や決定などは著作権法にかかりません。
引用が認められるケース
文芸作品や絵画など、あらゆるものは著作権で保護されています。
著作権法違反になりたくないからといって、全てを自分の言葉や絵などで伝えることは難しいですし、また不便です。
しかし適切な「引用」をすれば、著作権を侵害せずに他者の創作物を使用できます。
引用の条件については、著作権法第三十二条に書かれています。
公正な慣行に合うものであることや、報道などの目的のために正当な範囲内でなら引用できる、とされています。
しかし「公正な慣行」「正当な範囲内」など、はっきりいってどこからどこまでがOKなのか、どうやったらNGを出されずに引用できるのか、わかりにくいですよね。
パクリサイトと呼ばれたり、後々に問題となったりしないよう、引用のための正しいルールを覚えておきましょう。
「引用」で最も一般的であろう、文章の引用についてご紹介します。
自分の著作物と引用部分の内容的な主従関係があること
分量的・内容的に、自分の説を補強するために元の著作物を使っていることが必要です。
なお、引用部分が自説を書いた部分より多くても、内容的に必要な引用であれば主従関係があるとみなされます。
かぎかっこなどで引用部分がわかること
自分の意見と、引用元の文章が入り混じっているような書き方はNGです。
引用部分を四角く囲ったり、
かぎかっこで引用した文章を示したり、
『引用したテキスト引用したテキスト引用したテキストですよ』
あるいはダブルクォーテーションでくくったり、
❝引用したテキスト引用したテキスト引用したテキストですよ❞
――上記のような方法で、引用部分を明らかにする必要があります。
引用部分を示したあとに、誰のどの著作物かわかるように表示すること
先ほど示したような形で文章を引用したあとに、引用元の文章が何に掲載されていたかをきちんと示します。
雑誌に載っていた文章を引用した場合は、例えば下のような形で示します。
引用したテキスト引用したテキスト引用したテキストですよ
(雑誌『雑誌名ですよ』◎◎年〇月号 「タイトルですよ」(山田A子・著)より)
ウェブから文章を引用する場合は、ウェブサイト名・記事名や著者名、URLなどが必要になります。
日付も重要です。できることなら記事が更新された日に加え、引用者がサイトにアクセスした日も書きましょう。
ウェブ上の記事はサイト内で位置を移動したり、削除されたりというということが頻繁に起こります。引用者がアクセスした日にはその場所に記事があった、ということを示すためにもアクセス日を書いておいたほうが良いのです。
❝引用したテキスト引用したテキスト引用したテキストですよ❞
(引用元:田中B男「『記事名ですよ』サイト名ですよ」(更新日◎◎年〇月)
http://~~~ (参照日〇〇年△月××日)
ただし、残念なことにインターネットからの情報には、信頼性や信憑性に乏しいものが多くあります。引用する際には、情報の確かさを慎重に見極めてからにしましょう。
引用という形式であっても、デマ・流言飛語・不確かな情報を載せているサイトの信頼性もまた、疑わしくなるものだからです。
写真やイラスト、ロゴマークなどの著作権については今回は割愛します。
イラストやロゴマークについては、著作権のほかに商標権で守られているものもあります。
詳しく知りたいときは弁護士などの専門家に尋ねるか、いろいろな書籍で調べてみてください。
肖像権とは

写真や動画などにも著作権があります。それらは主に「撮った人」「撮影した人」の持つ権利です。
文章とは違い、写真などの画像や映像には「撮られた人」を保護する権利もあります。それが「肖像権」です。
たとえば、桜並木の下で友達同士でお酒を飲んだ写真を撮ったとします。
とても楽しかったし、よく撮れた写真だったので、あなたは自分のブログに記事をUPしようとします。
……ちょっと待ってください!
全員の許可を取りましたか?
あなたのお友達だけじゃないですよ? 後ろに写っている見知らぬおじさんやお子さんの許可も必要です。
ぼんやり写っていて誰かわからないレベルならいいですが、「あ、二丁目の酒屋のおじさんだ」とわかるものだったら肖像権の侵害になります。
それに「一緒に写真を撮ろうよ」に加えて「写真、ブログに載せるね!」ってちゃんと言いましたか?
両方の許可をもらっていない場合、肖像権侵害で訴えられる可能性があります。
芸能人の肖像権
もちろん芸能人にも肖像権はあります。
たとえば大好きな芸能人Aさんの写真を、自分のTwitterのアイコンにしている人もいますよね。芸能人本人や所属事務所から「許可する」という回答をもらっていなければ、立派な肖像権の侵害です。
芸能人の場合、人気商売ということもあり肖像権の侵害は見逃していることも多いです。ようするに黙認状態ということです。
一方では数が多すぎて取り締まりきれないという事情もあるでしょう。
見逃されているとはいえ、権利を侵害していることに変わりはありません。
撮影も画像・映像の使用も、被写体の許可を取ってからにしましょう。
なお、芸能人の写真は、自分で撮ったものでないかぎり、「誰か」が撮ったものです。
芸能人の写真を無断使用するときは、その誰か(多くは写真家など)の著作権を侵害していることにも注意してください。
著作権・肖像権を守ってサイトを運営しよう

著作権・肖像権をきちんと理解し、守ったうえでサイトやブログを運営しましょう。後々に起こるかもしれない、予想外の面倒ごとを避けるためにも大切です。
もし、「これは著作権上の問題になるかな?」「肖像権は大丈夫だろうか」と不安になったときは、弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。
Web制作に携わる上で知っておきたいライセンスについては、以下の記事を参考にしてください。
【参考記事】ライセンスに関してWebデザイナーが知っておくべきこと
- 最新記事