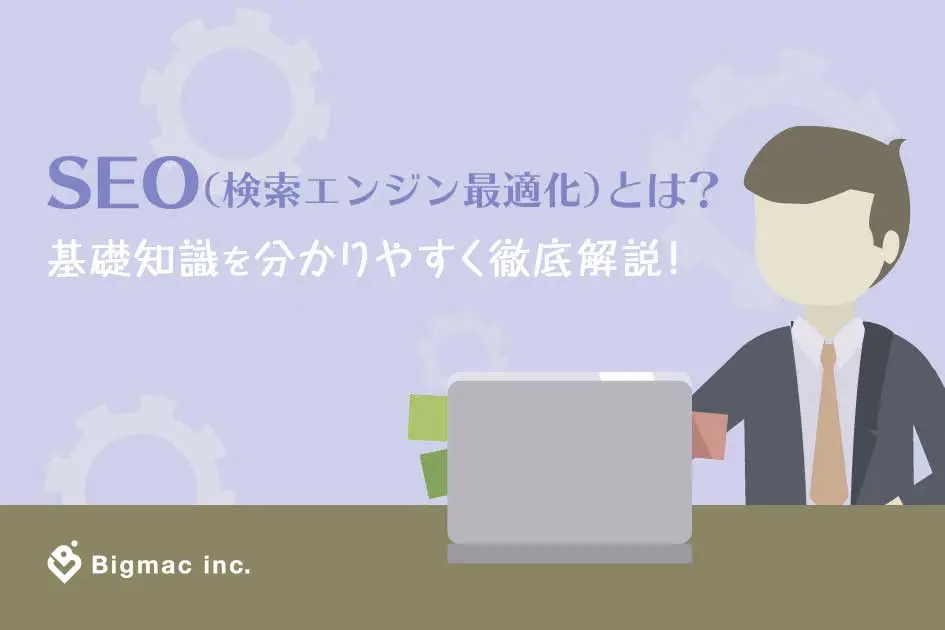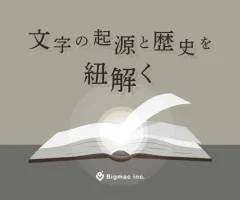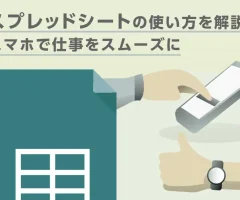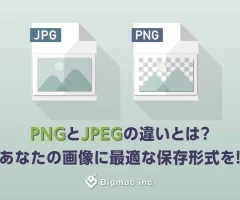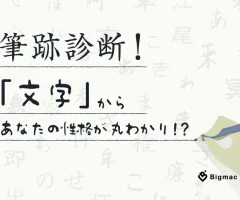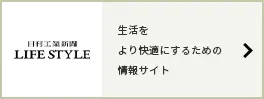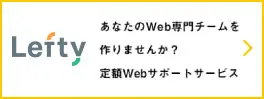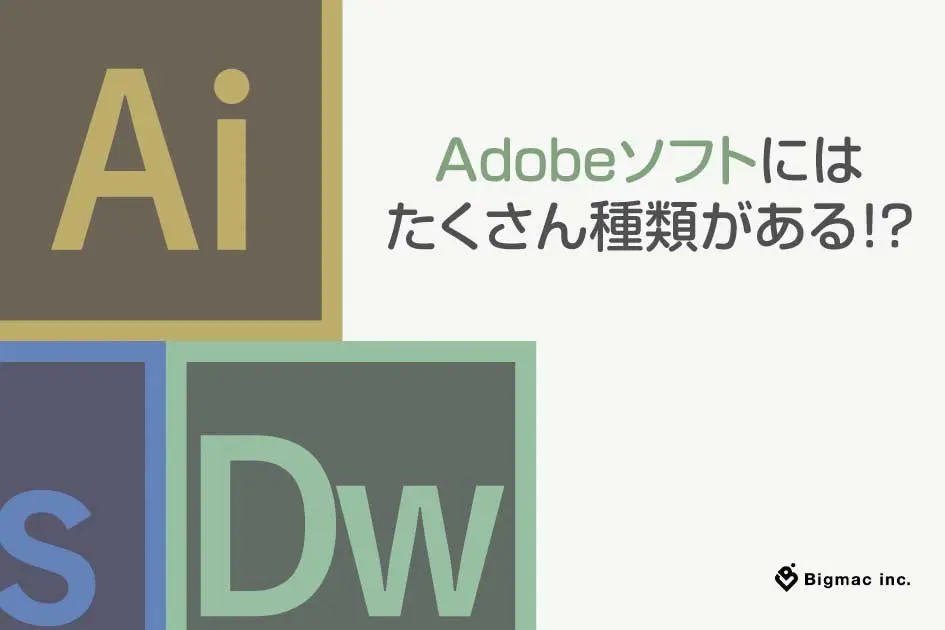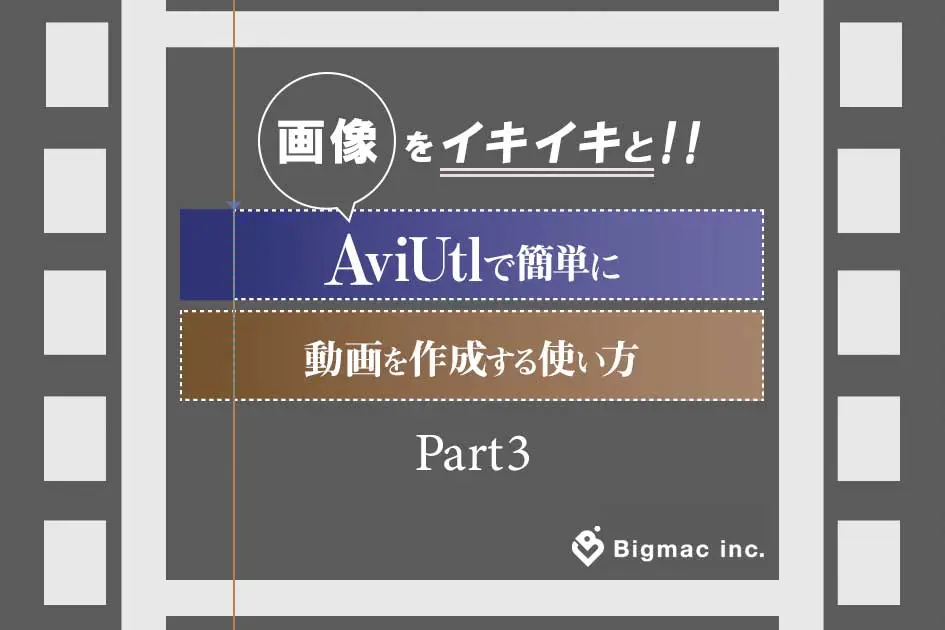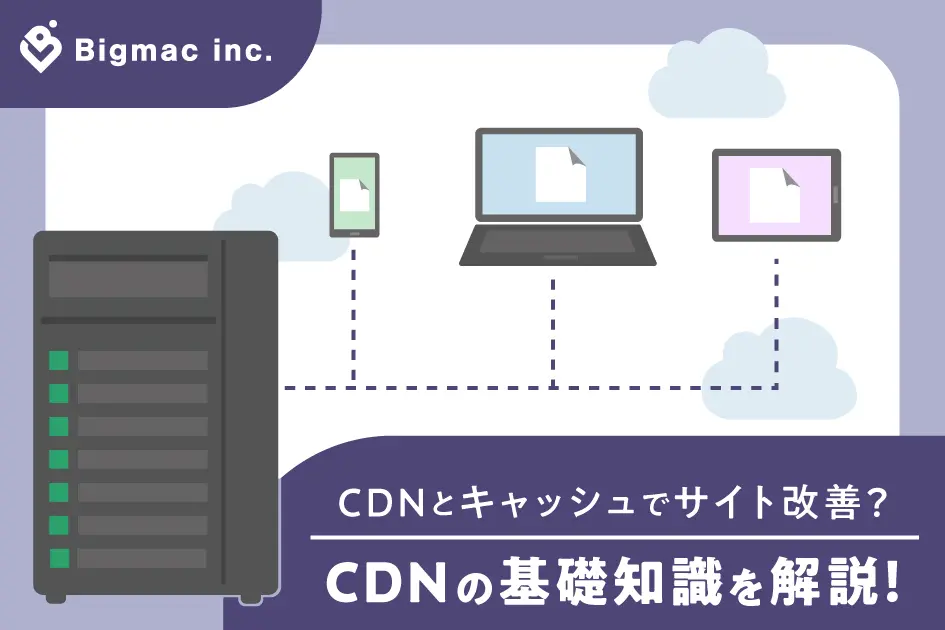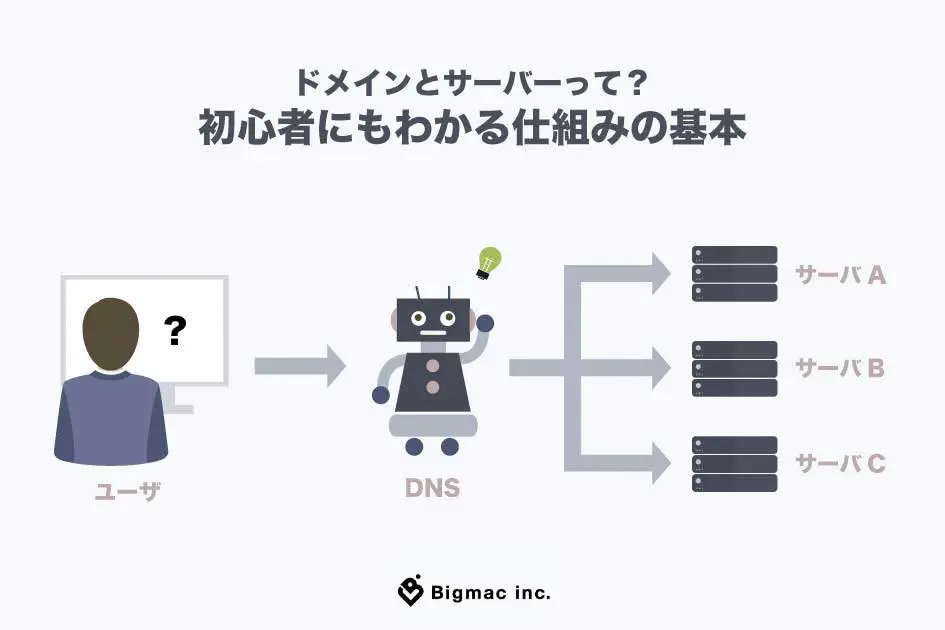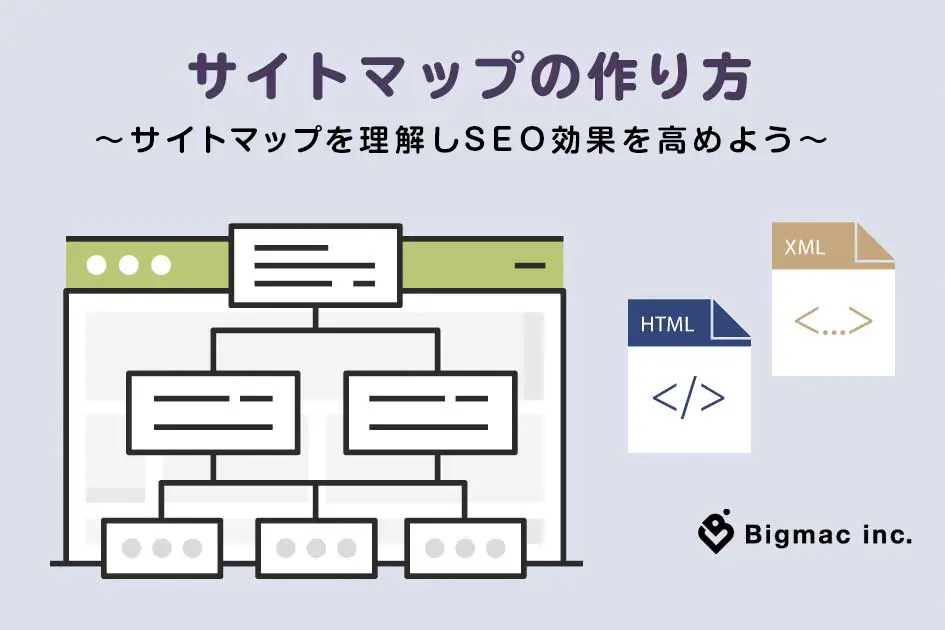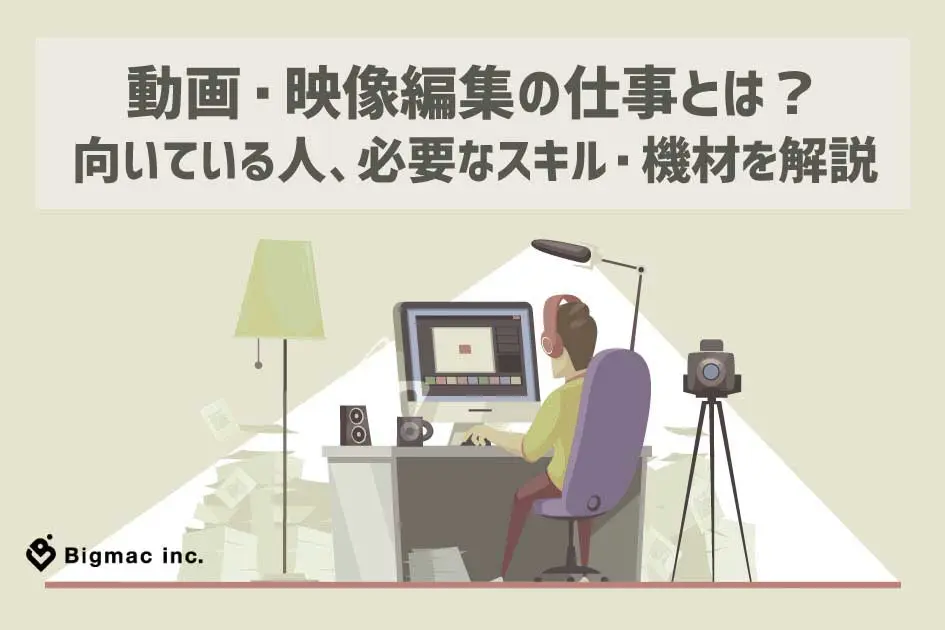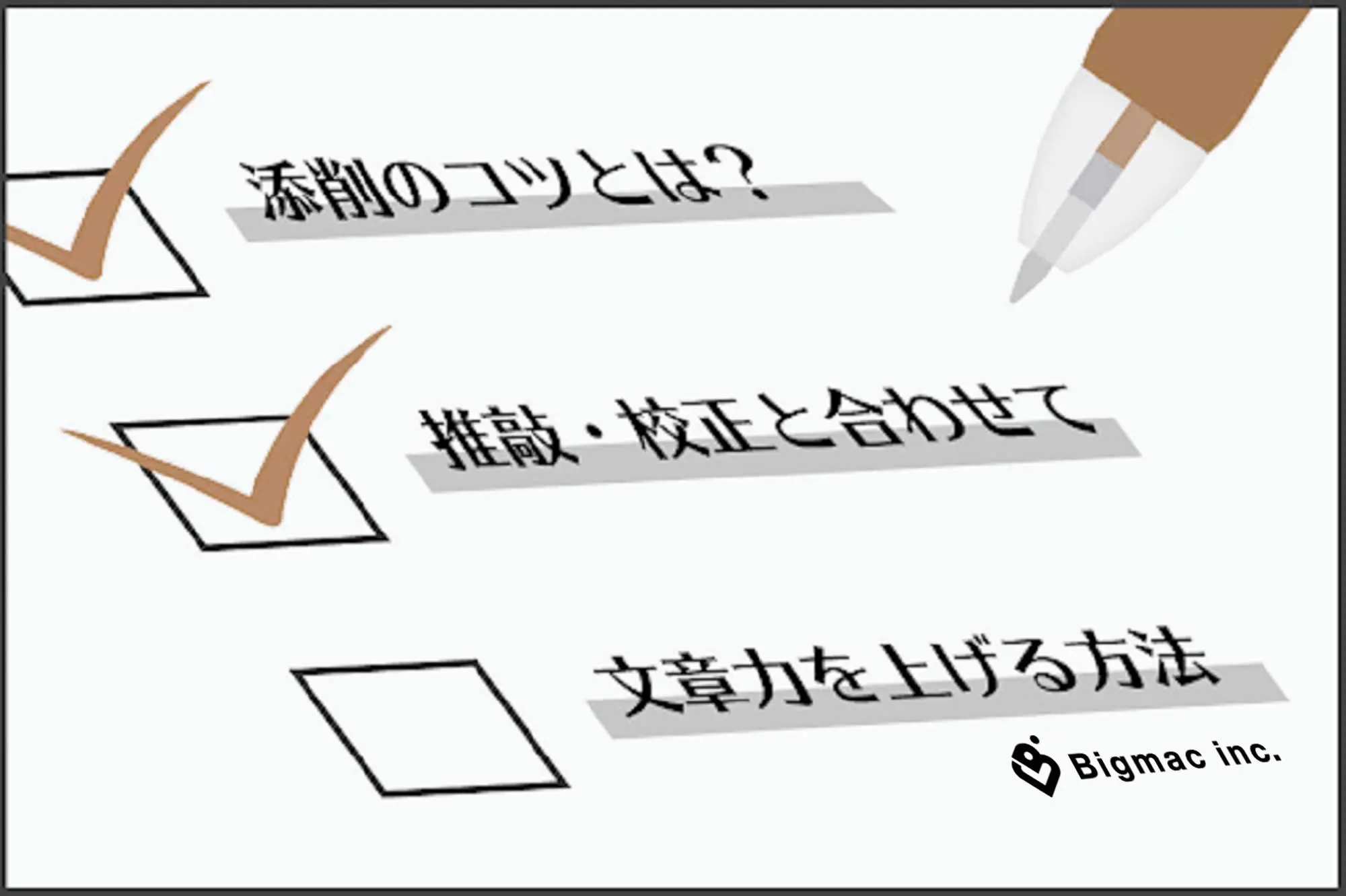
「添削」という言葉を聞いたことがあっても、その意味を、すぐに説明ができるでしょうか?「校正」や「推敲」とは、どう違うのでしょうか。
良い文章が書けないとお悩みの方に向けて、仕事や日常生活の中で役立ててもらえるように、より良く添削するためのコツをまとめました。
目次
添削とは何か?「校正」や「推敲」との違いも解説
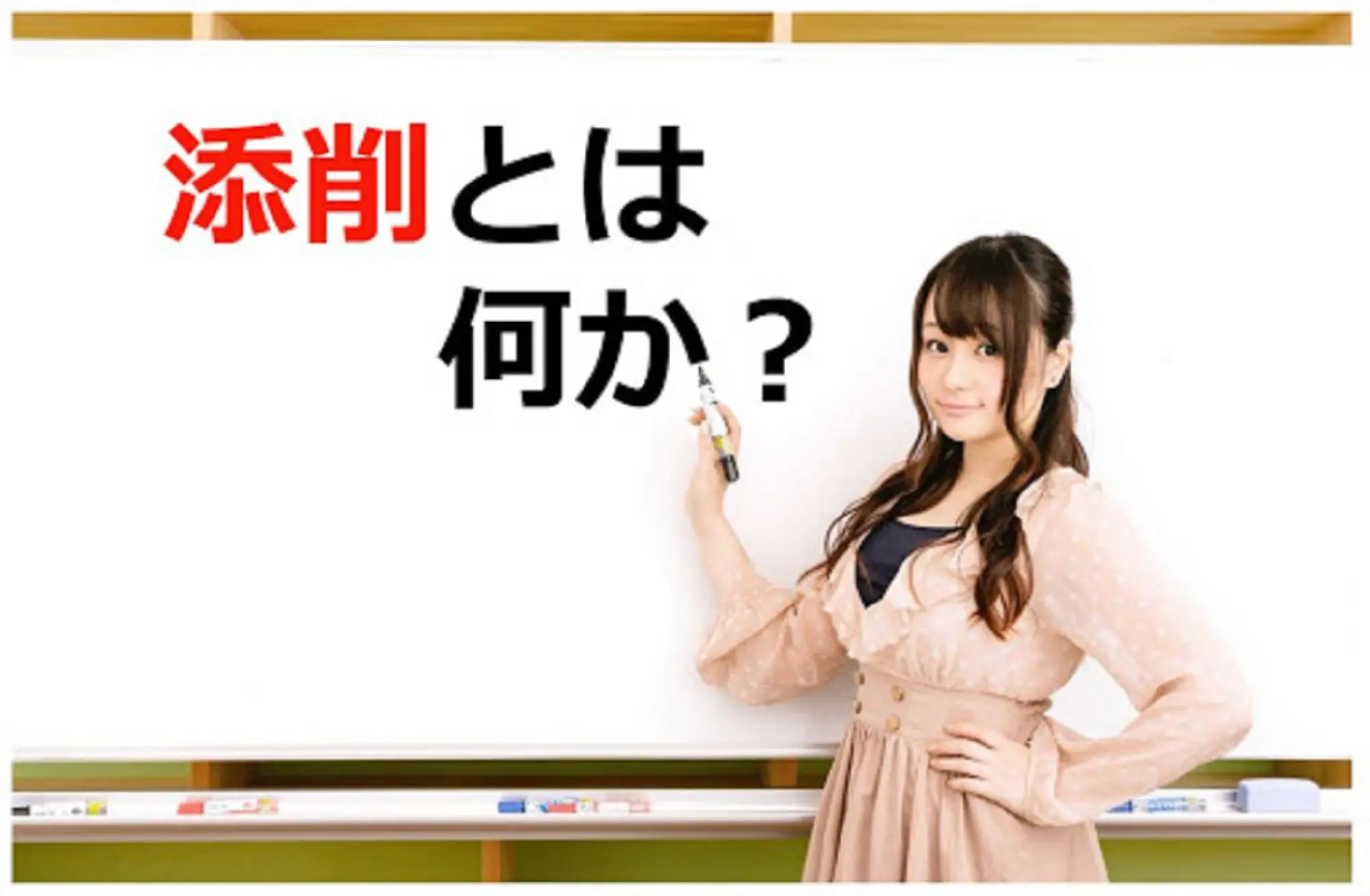
添削とは、他人が書いた文章の手直しをする行為です。『大辞林 第四版』には「他人の詩文・答案などに語句を添えたり削ったりして直すこと」と書かれています。
添削と聞くと、「学校や塾の先生が、子供の作文を直すための指導」、「学生時代の、小論文や試験」、「就職活動中、履歴書の志望動機や自己PRを他者にチェックしてもらった」といったイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、添削は特別で限定的な作業ではありません。例えば、一般的なビジネスシーンの「書類作成」などでも必須となります。
添削スキルを持つと仕事で有益
添削スキルは、部下が書いた書類を上司が確認する際や、お客様へ提示する資料を同僚間でチェックするなど、ミスやトラブルを防ぐために役立ちます。
書類作成において適切な添削が行えると、ミスやトラブルの防止に加え、書類(文章)をより良くするための視点も働くため、周囲の信頼を得ることにも繋がります。繰り返し修正することで、書類や文面の説得力が増すこともあります。
また、企業の広報でネットメディアが使用されるケースは年々増加しており、会社のWebサイトやブログ記事、メルマガやTwitterなどを担当する方も多いかと思います。不特定多数に向けた広報の文章作成は、内容や表現によっては、投稿後に大きなトラブルへ繋がる恐れがあるのも現実です。添削のコツを知り、文章力を向上させることは、必ず役に立つでしょう。
添削と似た言葉「推敲」「校正」「校閲」
「文章を直す」という意味で、添削と似た言葉に「推敲」「校正」「校閲」があります。違いがわかれば、文章の手直しをする方法を把握しやすくなります。
それぞれの意味を表にまとめました。
| 言葉 | 意味(大辞林 第四版より) |
|---|---|
| 添削 | 他人の詩文・答案などに語句を添えたり削ったりして直すこと |
| 推敲 | 詩文を作るとき、最適の字句や表現を求めて考え練り上げること |
| 校正 | 校正刷りと原稿を照合するなどして、文字や内容の誤りを正し、体裁を整えること |
| 校閲 | 印刷物や原稿を読み、内容の誤りを正し、不足な点を補ったりすること |
シンプルな表現ですと、以下のようになります。
- 添削:他人が書いた文章を手直しすること
- 推敲:自分で書いた文章を、自分で見直すこと
- 校正:「工程がひとつ前の文章」と「現段階の文章」を比較して直すこと
- 校閲:編集用語。原稿を、客観的事実と照らし合わせて、意味や内容の誤りを正すこと
添削・推敲・校正・校閲の意味を知っておくことで「文章改善の各工程で、何をするべきか」が理解しやすく、文章直しのスムーズ化や上質化が望めます。
添削のコツとは?

完璧な推敲をすることは、とても難しいとされています。理由は、自分で書いた文章だからこそ、客観的に見ることが難しくなるためです。
添削は、他者が文章を見るので、文字通り「客観的視点」です。しかし、「他者の視点」だけで見るのではなく、「添削のコツ」とも言うべきポイントを押さえることで、より適切で精度の高い添削ができます。
加えて、「添削のコツ」を身につけることは「客観的視点」の修練にもなり、自らの文章を直す際の「推敲」の技術にも通じますので、文章力向上にも繋がります。一度の添削・修正で文章を完成しようとはせず、複数回に渡ってのチェックが有効です。修正前と修正後の文章を見比べること、つまり「添削」と「校正」が文章力を向上させ、問題発見力を養います。
添削のコツ1.文章内で5W1Hが意識されているか?
5W1Hとは、情報伝達の6つのポイントを、英語と日本語でまとめた言葉です。添削時には、5W1Hがわかりやすくなっているかをチェックします。
- いつ(When)
- どこで(Where)
- だれが(Who)
- なにを(What)
- なぜ(Why)
- どのように(How)
上記の、6つの要素をはっきりさせることで、分かりやすい文章作成に繋がります。日常的なメモや会社の書類、小説や演劇の台本にも共通する、基本の要素と言われています。
また、5W1Hに「誰に(Whom)」と「いくら(How much)」を加えた6W2Hも、ビジネス向けに広まっています。
まとめると、以下の表のようになります。
| 日本語 | 英語 | ビジネス要素に置き換えた例 |
|---|---|---|
| いつ | When | 着手時間・期限・時間・納期・スケジュール |
| どこで | Where | 場所・位置・社内か社外か・出先 |
| だれが | Who | 組織・担当・中心人物・役職 |
| だれに | Whom | 相手・関係・人数 |
| なにを | What | 仕事の内容・種類・性質・分量 |
| なぜ | Why | 意義・目的・動機・理由・狙い・必要性 |
| どのように | How | 手段・方法・段取り・テクニック・進め方 |
| いくら | How much | 数量・予算・単価・範囲 |
添削のコツ2.テーマに沿った文章構成か?
テーマとは、文章を作る上での基調となる考えであり、読み手に伝えるべき事柄です。文章構成とは、テーマを読み手に伝わりやすくするよう文章の順番を組み上げることです。文章構成は、何の文章かによって様々な形があります。ビジネス上では、わかりやすさの追求や時間短縮を目的に、結論を最初に提示して、以下に結論に至る理由や情報を並べます。
しかし、例えばミステリー小説の場合、冒頭から犯人や解決のための証拠を提示してしまったら、読み手は興醒めしてしまいます。(一部例外作はあります)「読み手は何を求めているのか?」と、書き手が思考することは文章構成の基礎です。添削者は、文章を直すだけではなく、「書き手」の思考まで想像すると良いでしょう。
添削のコツ3.文章が無駄なくわかりやすくなっているか?
どれほど価値がある内容でも、読み手に読まれなければ価値が伝わりません。特に、ビジネスシーンでは「速さ」を求められることが多く、わかりにくい文章は避けられ、書き手の文章力が貧しいとして文章内容まで過小評価を受ける恐れがあります。
しかし、客観的視点が適切に働いていない書き手は、わかりにくい文章に無自覚になりがちです。添削する際は、以下の要素をチェックすると、文章のわかりやすさ向上に繋げられます。
- 読み返さないとわかりづらい表現はないか?
- 重複気味の書き方はないか?
- 同じ助詞や文末を連続して使っていないか?
- 長すぎて、複雑で煩わしい文や段落はないか?
- こそあど言葉(指示語)を多用していないか?
- 表記ゆれがなかったか?(同じ意味の言葉をバラバラの言葉で書くこと)
上記のようなポイントに注目して文章を読み、問題点を見つけるのが添削のコツです。黙読よりも、音読すると問題点は見つけやすいとも言われます。スムーズに声にできなかった点は、前後の文章込みで改善の余地があります。
添削のコツ4.文中の句読点が適切に使用されているか?
句読点とは、「句点【。】文末に使用する」と「読点【、】文の切れ目や、文の続きを明らかにするために使う」という、ふたつの記号を指す総称です。句点は「文末に使用する」という基準が明確なので、日本人なら使い間違いは比較的起こりません。読点は、使用法を間違えると文章の意味そのものが変質してしまうので、注意が必要です。
以下、例文を紹介します。
「浜田さんは食事しながら笑っている松本さんを怒った」
上記の文だと、浜田さんと松本さんのどちらが食事をしているのかが不明確です。
「浜田さんは、食事しながら笑っている松本さんを怒った」
上記のように読点を打つと、食事をしている松本さんに対し、浜田さんが怒ったことになります。
「浜田さんは食事しながら、笑っている松本さんを怒った」
上記だと、食事をしている浜田さんが、松本さんを怒ったことになります。
読点の使い方ひとつで、文章の読み方や意味が変わってしまいます。
しかし、書き手本人は脳内イメージが確立してしまっているためか、誤読される危険性に気づきにくい場合があります。
読点ひとつに対しても、添削者は客観的視点を持って読み取り、書き手に文章改善を提案することが求められます。
添削のコツ5.専門用語を多用していないか?
専門用語を使うと、用語の意味を知らない人にとっては読みにくい文章になりがちです。読み手が全員その専門用語を知っている、例えば社内の書類の場合は良いですが、書き手は「読み手がこの専門用語を知らない」ことを意識して書く必要があります。
そのためには、専門用語に補足説明を加えると良いでしょう。
以下の例文を見比べてみてください。
・例文1
「ノイシュヴァンシュタイン城は、ワグネリアンであるルートヴィヒ2世が自らの作品として建設させた城である。だが彼は、172日間しか居住しなかった」
・例文2
「ノイシュヴァンシュタイン城は、ルートヴィヒ2世が建設させた城である。
ワーグナーの創作するオペラに心酔する『ワグネリアン』であった彼は、ワーグナーの作品を「自分たちの作品」と呼んでいただが、ワーグナーは自らの作品に口出しすることを許さなかった。
そのため、ルートヴィヒ2世は「自らの作品」としてロマンティックな城を造ろうと、ノイシュヴァンシュタイン城を建設させたのである。
だが彼は、172日間しか居住しなかった。」
例文2は、「ワグネリアン」が何であるかの説明を書き加えているので、例文1より分かりやすい内容になっています。
ですが、専門用語全てに補足説明を加えることは、おすすめできません。
補足説明は冗長になることがあります。
専門用語の意味を知っている人にとっては、退屈な文章だと感じるかもしれません。
補足説明が多く、結論が分かりづらい内容になっていないか、注意しましょう。
文章校正ツールや校正サービスとは?

膨大な量の添削をすると、誤字脱字の見落としがなかったか、気になるのではないでしょうか。「誤字脱字」「表記ゆれ」などのミスを見つけてくれるのが「文章校正ツール」です。
日本語の文章だけではなく、英語の文章を校正してくれるツールがある他、文章を添削してくれるサービスもあります。
無料のツールも含めて、簡単にご紹介します。
Wordの文章校正ツール
Wordでは、文章校正ツールが標準機能で付いています。難しい設定なども必要なく、「誤字脱字」「表記ゆれ」だけでなく、「タイプミス」「スペルミス」「言い回しの間違い」も自動でチェックしてくれるので、便利です。
チェック機能で単語や文の下部に波線が出ることがありますが、その波線を右クリックすると、修正候補が表示されます。
まとめて文章チェックするための「スペルチェックと文章校正」という機能もあり、この機能を使うほうが、時間短縮に繋がります。
Ginger
Gingerは、英文をチェックしてくれるツールです。Wordでもチェックしてくれますが、基本的なスペルチェックしかできません。
英文自体の間違いをチェックするだけではなく、言い換え表現を提案してくれるので、機械翻訳したときの不自然な英文を直すこともできます。
ブラウザの拡張機能をインストールすることで、GmailやYahoo!メールを使っているときに自動で英文をチェックしてくれます。
ペーパーハウス
校正・校閲を専門としている会社で、35年以上の実績があるそうです。添削をする時間がない、校正ツールでは物足りない、専門家の手を借りたいなどワンランク上の質が必要なら、見積依頼をおすすめします。
添削のコツまとめ
添削のコツとは、「文章をより良くするため、どこに注目するか」を理解して、客観的視点で文章の問題点を洗い出すことです。単に文章を添削するのではなく、「書き手と読み手」両方の思考と気持ちを察し、文章を通して「人」を想像していくことが、文章力の成長に繋がります。
文章力を上げるための専門講座を受講することも成長に繋がりますが、まずは添削のコツを身に付けて行きましょう。
▼参考記事はこちら
- 最新記事