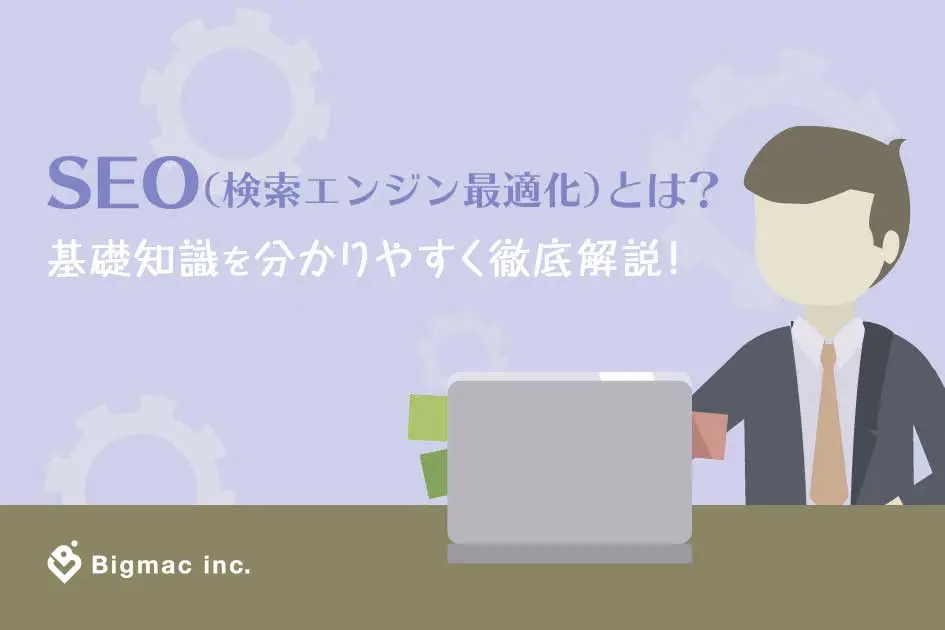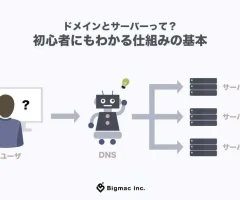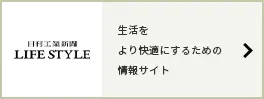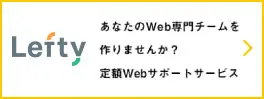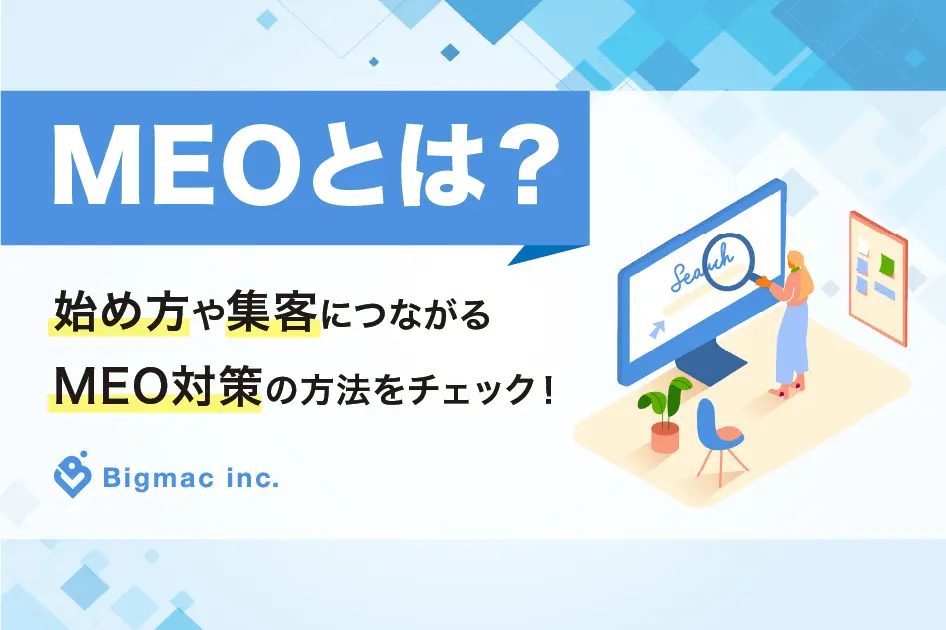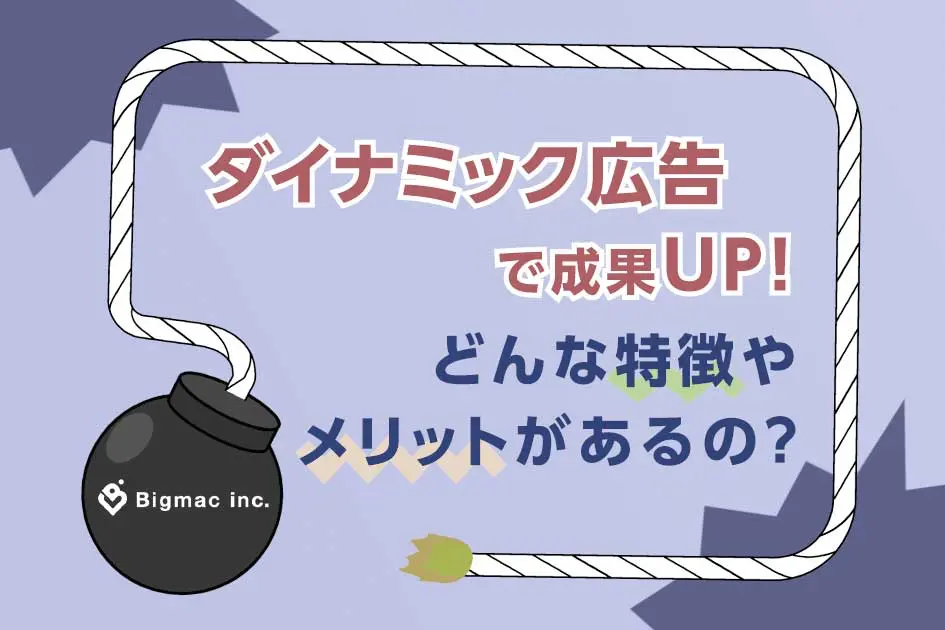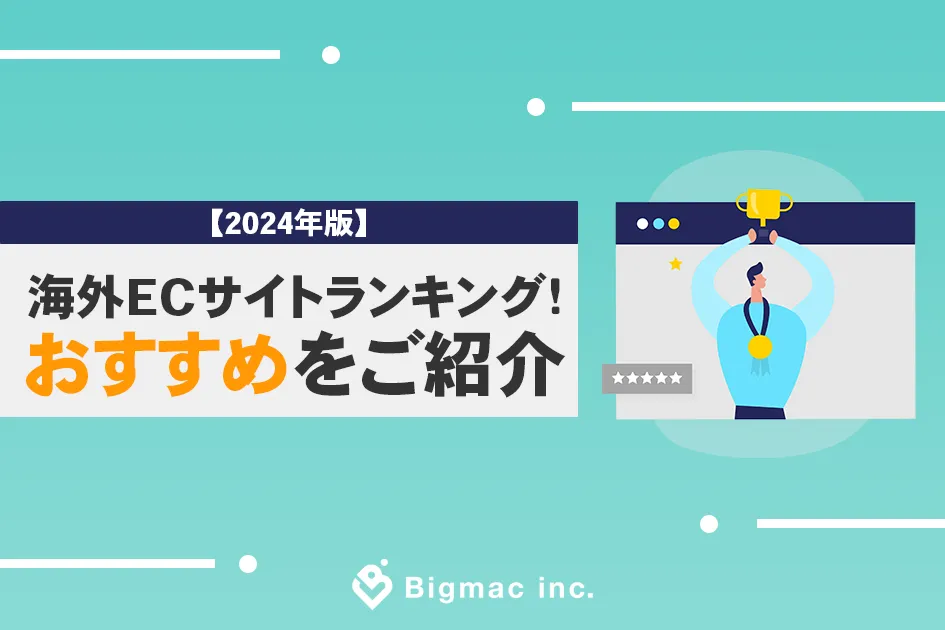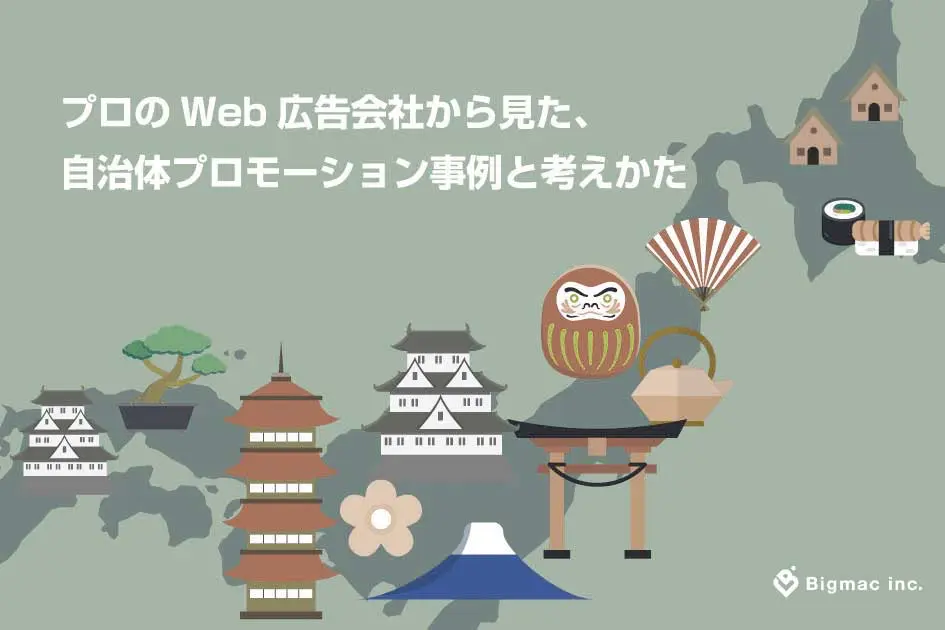
広告会社からお客様として見た場合。かつての自治体は、「お堅くて融通が効かず、うまみのある仕事がない。」といわれてきました。しかし現在、地方創生が叫ばれるほど事情が変わっています。
自治体職員だけでは解決できないコミュニケーション課題が山積みとなり、広告業界を頼るということが増加しています。具体的には、下記ケースで広告業界に声が掛かることが多いでしょう。
・リスティング広告に代表されるインターネット広告
・テレビ、新聞、ラジオ、雑誌などのマス広告
・広告を含めPR対応すべて
・ウェブサイト制作
福井県福井市に本拠を置くBigmacは、東京や都市部の案件、地元民間企業のインターネット広告やウェブプロモーションを支援させて頂いております。また、地元・福井の市区町村や一般社団法人などの外郭団体も、数多くインターネット広告で支援させて頂いております。
そんなプロのWeb広告会社から見た、自治体プロモーションについて記事にしました。事例や考えかたについて記しておりますので、自治体の職員様やご担当者様に参考になればと考えます。
目次
民間企業案件と自治体案件では仕事の進めかたが違う
自治体の広告案件と民間企業の広告案件を比べると、仕事の進め方がまったく違います。たとえ広告会社側の提案内容がどれほどよくても、時期やルールが守られないとNG。その特徴を踏まえ、ニーズに合う対応が求められます。
民間案件の常識
・企画内容が一番である
・断られる理由が聞けない
・柔軟な対応が求められる
自治体案件の常識
・企画内容以外も重要
・断られる理由が聞ける
・厳格な対応が求められる
最新情報をいち早くお届け!
無料会員登録していただくと、
会員限定の特別コンテンツ記事を最後まで
読むことができます!
その他、更新情報・イベント情報を
お届けいたします。
自治体が広告会社に求めるニーズをつかむ
自治体ビジネスの予算の使われかたは仕様書に書いてある
自治体予算の出どころを例に挙げると、官庁から交付されるもの、地場の税収が財源になっているものがあります。そして、これらの予算を担当部署で確保するために、使いみちや効果を記した「仕様書」を作成するのが通常の流れです。
自治体の支援をする広告会社としては、仕様書の内容を適切に理解および解釈することが不可欠です。また、各担当者は広告の知識がない状態で仕様書を作ることは大きな困難を伴います。新規事業の場合は特に、仕様書作成から参加することも求められることも多いです。
民間企業へ提案するアイディアは自治体には響かない
上記の仕様書では、本質的な課題が含まれていないケースや、施策が細かく規定されすぎて柔軟性がないケースなど広告会社から見て「あまり良い仕様書とは言えないな…」と思う場合が少なくありません。
仕様書の作成者は自治体職員。あくまでも行政サービスの専門家・プロであって、広告やプロモーションのプロではありません。柔軟性が限られる中で、いかに最大限のクリエイティビティを発揮できるか?欠けている要素をいかに盛り込むか?
その提案力が広告会社には求められると考えています。
提案時点でも受注してからも極力 、専門用語は使わない
無事に受注し、プロジェクトが開始されたとしても…。プロジェクト開始後、双方の考えや期待値がすれ違うことがあります。
こうしたすれ違いの状態に陥らないための工夫が必要になります。
・マーケティング用語を使わずに分かりやすく説明する
・仕様書に書かれていない、自治体職員のニーズに合わせたことを聞く
具体的にはこれらのスキルが必要となるという実感があります。こうやって自治体と二人三脚でプロジェクトを進め、お付き合いしていこうという姿勢が大事です。そうすれば次年度にまたお声がけ頂けることにもなりますし、そのときはより良い条件をご提示頂けたり、自治体担当者との関係性や知識ができあがっている分、やりやすくもなります。
地方自治体や自治体職員が広告会社に求める役割
そもそも自治体の首長や担当者は、何に課題を感じ、何を求めて広告会社に依頼するのでしょうか。それは、民間企業と異なるはずです。例えばコストカットや単純業務の外注化をしたいということではありません。
人口減少・少子高齢化など、自治体が取り組む課題はより複雑になっています。一方で、その根幹は「人と人とのコミュニケーションを円滑にする、共感を得て行動を喚起する」こと。自治体職員は、職に就いたときからずっと自治体職を全うすることがほとんどです。
そうすると、行政手続きの専門知識やスキルは身につくものの、課題解決や目的達成のために適切なコミュニケーション活動を行う経験やノウハウは持ち合わせていないのです。広告会社へ依頼する目的は、課題解決や目的達成の知見である。その役割をしっかり理解していなければいけないと考えています。
インターネット広告会社に期待されている役割の例
・売れる特産品を作りたい
・観光を盛り上げたい
・シビックプライド(住民が地元に対する誇りや愛着)を高めたい
・移住を促進したい
上述したように、自治体向けの提案は民間企業向けの提案と比べ、響くポイントが違います。だから、自治体向けにどのように企画提案をしていくか?その違いを見極める必要があります。
企画提案時のポイント
具体的には、企画提案時には下記に留意します。
・その自治体の課題を正しく理解するための入念なリサーチ
・自治体は万人に平等にサービスせねばならない立場であることの理解
・専門用語なしで自治体担当者や上長が価値を理解できる企画書の内容
同様に、専門用語なしで価値が理解できるプレゼンテーション
提案までの流れ
提案までは下記のような流れになります。
- 挑む価値があるか?を見極める
- 参加資格があるか?を知る
- 情報収集と仮説分析
開示された情報や資料を元にしたり、関係者へのヒアリングを行うなどして、情報を集めます。情報を集めることによって国や自治体のニーズがつかめてきますから、競合他社の強み・弱みや自社の強み・弱みと照らし合わせます。自社の提供価値がどう提示できるか?を自問し、競合他社と比べて優位性のある訴求点を導きます。
自治体ビジネスの常識を知れば、提案がきちんと通りやすくなる
自治体ビジネスにはセオリー=常識があります。その常識を知り、その常識どおりにことを進めなければ、せっかくの企画も水の泡になってしまいます。
例えば、受注方法として一般的には公募入札が有名ですが、その他にもプロポーザル案件や逆指名案件が存在します。見積り価格の安さだけが受注要因にはならず、専門性が活かせる有利な条件で提案ができる場合も実は多いのです。
また、細かい年間スケジュールをしっかりと把握しておくことも重要。基本的には今年の提案が翌年度の案件になるようなスケジュール感で進むことが一般的。そこで、実はさらに細かい年間スケジュールを把握しておくことで、自治体が望む訪問やヒアリングをする時期・回数・内容を導き出すことができます。
自治体が望む時期は四半期サイクル
4月~6月期:翌年度の予算見通し
外部情報の提供で信頼関係を構築すべき時期です。下記のような情報を提供することが望まれます。
・人事の確認
・実施例や先進事例
・前年度の満足度
7~9月期:予算見積もり
発注形態の確認をする時期です。自治体担当者との綿密な連携を心がける必要があります。
・継続または新規事業の意見交換
・企画提案の実施
・参考見積もりの提出
10~12月期:予算案
財務部門とのヒアリング支援を行う時期です。
・統計や類似資料の提供
・プレゼン支援
1月~3月期:予算の議決
次年度の受注の準備時期です。次年度に向けた1年の集大成と言えます。
・業者選定時期
・発注形態の再確認
・人事異動予定の確認
ありがちな勘違いや失敗に対策をする
提案が噛み合わない場合
提案事業を裏付ける統計データや、他地域での先進事例の成果を報告する必要があります。
提示された内容に合わせて企画する場合
仕様書作成に関わり、参入障壁を仕込む必要があります。例えば参加資格や業務内容、評価基準を制限するなどです。
接待を断られる場合
接待はこのご時世にそぐいません。情報提供が一番重宝されると心得る必要があります。下記に漏れがないように自問し、自治体との情報提供を図ります。
・人口規模が同じ自治体の事例はないか?
・地域特性が同じ自治体の事例はないか?
・隣接する自治体の動きはどうなっているか?
自治体から問い合わせが来るようにしたい場合
研究会を開催するのが有効です。信頼が積み重なり、自治体から声がかかりやすい状況が作られます。
研究会開催の工夫例
・参加費用を無料にする
・自治体職員が参加しやすいよう午後からの参加に対応する
・自治体職員自体をゲストに呼ぶ
・自社のPRはしない
・年3~4回、定期に開催する
まとめ
地方創生と呼ばれ、都道府県や市町村を含む官庁や地方自治体で、多くの予算と各担当者の思いが交差しています。その中で、広告関連会社の企画力や表現力が求められているのです。
日本には、まだまだ外へ知られるべき多くの資源があります。それを誰よりも知るのが、地元の地方自治体職員。広告会社と自治体との正しい連携によって、より国内が活性化することを願います。
- 最新記事